「机の上が領収書だらけで整理が追いつかない…」「確定申告の時期になると、レシートを探すのに一苦労…」そんな経験はありませんか?
クラウド会計ソフトを使えば、スマホでレシートを撮影するだけで自動的に帳簿に記録され、領収書の山とはお別れできます。「会計ソフトなんて難しそう」と思われがちですが、今のクラウド会計は驚くほど簡単で、税理士さんとの連携もスムーズになるんです!
クラウド会計ソフトって何?従来との違いは?
クラウド会計ソフトとは、インターネット上で使える会計ソフトのことです。パソコンにソフトをインストールする必要がなく、スマホやタブレットからでも操作できます。
従来の会計管理との違い
紙の帳簿:手書きで記録、計算ミスのリスク、保管場所が必要
パソコンソフト:手入力が中心、バックアップが面倒、外出先で確認不可
クラウド会計:スマホ撮影で自動入力、自動計算、いつでもどこでも確認可能
まるで家計簿アプリの法人版のような感覚で、簡単に使えるのが最大の特徴です。
こんな方におすすめ
特に効果を実感できる方
個人事業主として開業したばかりの方
領収書の整理や入力作業に時間を取られている方
税理士さんに資料を渡すのに時間がかかっている方
売上や経費をリアルタイムで把握したい方
複数の銀行口座やクレジットカードを事業で使っている方
要するに「数字の管理を楽にしたい」すべての個人事業主・中小企業経営者におすすめです。
代表的なクラウド会計ソフト3選
初心者におすすめの代表的なクラウド会計ソフトをご紹介します。どれも基本機能は充実しており、無料プランもあります。
1. freee(フリー)
おすすめポイント
会計知識がなくても使いやすい設計
質問に答えるだけで確定申告書が完成
レシート撮影の精度が高い
銀行口座・クレジットカードとの自動連携
料金
スターター:月額980円(年払いで月816円)
スタンダード:月額1,980円(年払いで月1,648円)
無料プランもあり(機能制限あり)
こんな方に最適
会計が初めてで、とにかく簡単に使いたい方
2. マネーフォワード クラウド会計
おすすめポイント
家計簿アプリ「マネーフォワード ME」と同じ会社で安心
他のクラウドサービス(給与計算、請求書作成)との連携が充実
AI機能による自動仕訳が優秀
サポート体制が充実
料金
スモールビジネス:月額2,980円(年払いで月2,480円)
ビジネス:月額4,980円(年払いで月4,180円)
無料プランもあり(50仕訳/月まで)
こんな方に最適
ある程度事業が軌道に乗り、総合的なバックオフィス業務を効率化したい方
3. やよいの青色申告オンライン
おすすめポイント
老舗会計ソフト会社「弥生」の安心感
初年度無料キャンペーンが充実
簿記知識がある方にとっては使いやすい
サポートが手厚い(電話・メール・チャット)
料金
セルフプラン:年額8,000円(初年度無料)
ベーシックプラン:年額12,000円(初年度6,000円)
トータルプラン:年額20,000円(初年度10,000円)
こんな方に最適
コストを抑えて始めたい方、従来の弥生製品に慣れている方
スマホでレシート撮影!実際の使い方
最も革新的な機能である「レシート撮影機能」の使い方を、freeeを例に詳しく説明します。
Step 1: スマホアプリをダウンロード
各会計ソフトには専用のスマホアプリがあります。App StoreやGoogle Playで「freee」と検索してダウンロードしましょう。
Step 2: レシートを撮影
1. アプリを開いて「レシート撮影」をタップ
2. レシートをスマホのカメラで撮影
3. 四隅がしっかりと画面に収まるように調整
4. シャッターボタンを押して撮影完了
撮影のコツ
明るい場所で撮影する
レシートは平らに伸ばす
文字がぶれないように固定して撮影
レシートの四隅がすべて画面に入るようにする
Step 3: AIが自動で読み取り
撮影すると、AIが以下の情報を自動で読み取ります:
– 日付
– 店名
– 金額
– 商品名(明細がある場合)
読み取り精度は非常に高く、手書きのレシートでもかなり正確に認識します。
Step 4: 勘定科目を確認・修正
AIが「この経費は○○費だと思います」と勘定科目を提案してくれます。間違っていれば簡単に修正できます。
よくある勘定科目の例
コンビニ弁当 → 会議費
ガソリン代 → 車両費
文房具 → 消耗品費
会食代 → 接待交際費
Step 5: 保存完了
内容を確認して「保存」ボタンを押せば、自動的に帳簿に記録されます。所要時間はたったの30秒程度です!
銀行口座・クレジットカードとの自動連携
クラウド会計の真価は、銀行口座やクレジットカードと連携して自動で取引を取り込むことです。
連携の設定方法
1. 会計ソフトの管理画面で「口座連携」を選択
2. 連携したい銀行を選択
3. インターネットバンキングのID・パスワードを入力
4. 連携完了
連携可能な金融機関
メガバンク(三菱UFJ、みずほ、三井住友など)
地方銀行(各地の主要銀行)
ネット銀行(楽天銀行、PayPay銀行など)
信用金庫
主要クレジットカード会社
自動取り込みの便利さ
– 毎日自動で取引データを取得
– 入金・出金を自動で帳簿に反映
– 重複取引の自動チェック
– 残高の自動照合
これにより、現金取引以外はほぼ自動で帳簿が完成します。
税理士さんとの連携がスムーズに
クラウド会計を使うと、税理士さんとの連携が劇的に改善されます。
従来の方法との比較
従来の方法
領収書を月末にまとめて整理
手書きまたはExcelで帳簿を作成
紙の資料を税理士事務所に持参・郵送
税理士さんが再度データ入力
質問があれば電話・メールでやり取り
クラウド会計の場合
日々の取引が自動で帳簿に記録
税理士さんも同じデータをリアルタイムで確認可能
質問や修正も画面上で完結
確定申告書の作成も効率的
具体的なメリット
経営者側のメリット
資料準備の時間が大幅短縮
いつでも経営状況を数字で確認可能
税理士さんからのアドバイスが早い
税理士さん側のメリット
データ入力作業の削減
リアルタイムでの経営アドバイスが可能
繁忙期の作業負荷軽減
結果として
税理士報酬の削減可能性
より高度なアドバイスを受けられる
コミュニケーションの頻度・質が向上
導入時の注意点とコツ
最初の設定は丁寧に
– 開始残高の設定は正確に行う
– 勘定科目の設定は税理士さんと相談
– 消費税の設定(課税事業者か免税事業者か)を確認
慣れるまでは並行運用
最初の1-2ヶ月は、従来の方法と並行してクラウド会計も入力し、慣れてから完全移行するのが安全です。
定期的なデータチェック
– 月末には必ず残高確認
– 勘定科目の間違いがないかチェック
– 税理士さんとの定期的な確認
セキュリティに注意
– パスワードは複雑なものを設定
– 二段階認証を有効にする
– 不要になったアクセス権限は削除
導入効果の実例
美容院経営のCさんの場合
導入前
– 月末に3時間かけて領収書整理
– 税理士さんへの資料準備に半日
– 経営数字の把握が遅れがち
導入後
日々の入力時間が1日5分程度
税理士さんとの打ち合わせがオンラインで30分
リアルタイムで売上・経費を把握
年間効果
事務作業時間:年間50時間削減
税理士報酬:年間6万円削減
経営判断の精度・スピード向上
コンサルタント業のDさんの場合
導入前
– 出張費の精算が月末にまとめて大変
– 請求書と入金の照合が手作業
– 確定申告時期に資料探しで苦労
導入後
出張先でスマホ撮影、その場で処理完了
請求書と入金が自動で照合
確定申告書がワンクリックで作成
年間効果
確定申告準備時間:20時間→2時間
領収書の紛失:ゼロ
ストレス大幅軽減
よくある質問と回答
Q: 会計知識がなくても使えますか?
A: はい、大丈夫です。最近のクラウド会計は「借方・貸方」などの専門用語を使わず、「売上」「経費」といった分かりやすい言葉で操作できます。
Q: データが消えてしまう心配はありませんか?
A: クラウドサービスは複数のサーバーでデータを保管しているため、パソコンが壊れてもデータは安全です。むしろ従来のパソコンソフトより安全と言えます。
Q: インターネットがないと使えませんか?
A: 基本的にはインターネット接続が必要ですが、スマホアプリなら一時的にオフラインでも撮影・入力でき、接続時に自動同期されます。
Q: 税理士さんが嫌がることはありませんか?
A: 最近は多くの税理士さんがクラウド会計を推奨しています。導入前に相談すれば、きっと協力してくれるはずです。
まとめ:デジタル化で経理業務を劇的に効率化
クラウド会計ソフトは、面倒な経理業務を劇的に効率化してくれる強力なツールです。
導入の第一歩
まずは無料プランで各サービスを試用
自分の業種・規模に合ったサービスを選択
税理士さんと相談しながら本格導入
慣れてきたら高度な機能も活用
「紙の領収書に振り回される日々」から「スマホ一つで完結する効率的な経理」へ。この変化は、あなたのビジネスにもっと集中する時間を生み出してくれます。
ぜひ今日から、クラウド会計で領収書の山からの解放を体験してみてくださいね!
シリーズ完結
「初めての○○」シリーズ、いかがでしたでしょうか?
どの記事も「今日から始められる」をコンセプトに、デジタルツールの導入について書かせていただきました。
皆様のビジネスにお役立ていただければ幸いです!
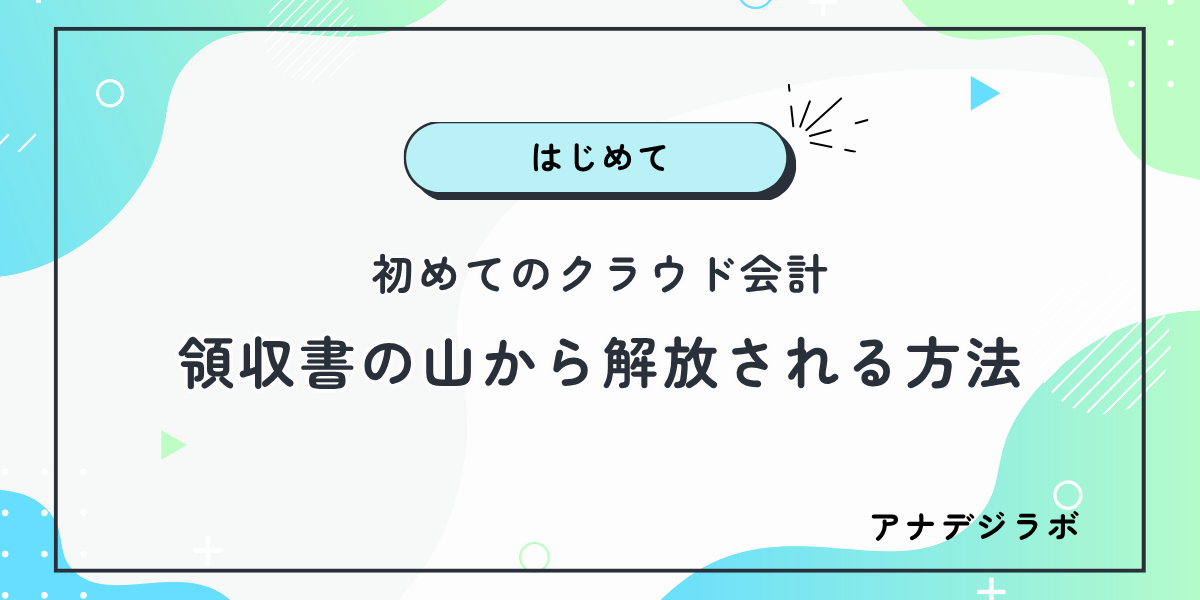
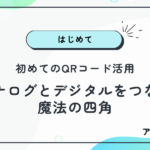
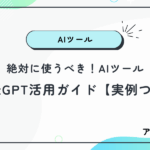
コメント